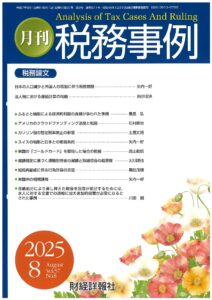税務QA281号4-35頁、税務研究会。
税理士業務に行うにあたり、納税の猶予と換価の猶予のいずれかを選択できる場合があり、通常業務として徴収実務を行わない私たち税理士が、判断を戸惑うことが多々あります。
結論から言いますと、いずれの適用も可能である場合には「納税の猶予」の適用を優先して、検討を行うべきです。
なぜなら、延滞税の取扱いをはじめとして、滞納処分の取扱いで、納税者に有利となる場合があるのが「納税の猶予」だからです。
しかしながら、「納税の猶予」については、申請期限が限られているものもあり、知らぬ間に申請期限が徒過していることも少なくないようです。
このため、本稿におきましては、納税の猶予と換価の猶予の租税実務についてとりあげることし、税務調査等で課税が遅延した場合などの納税の猶予あるいは換価の猶予をとりあげることとします。